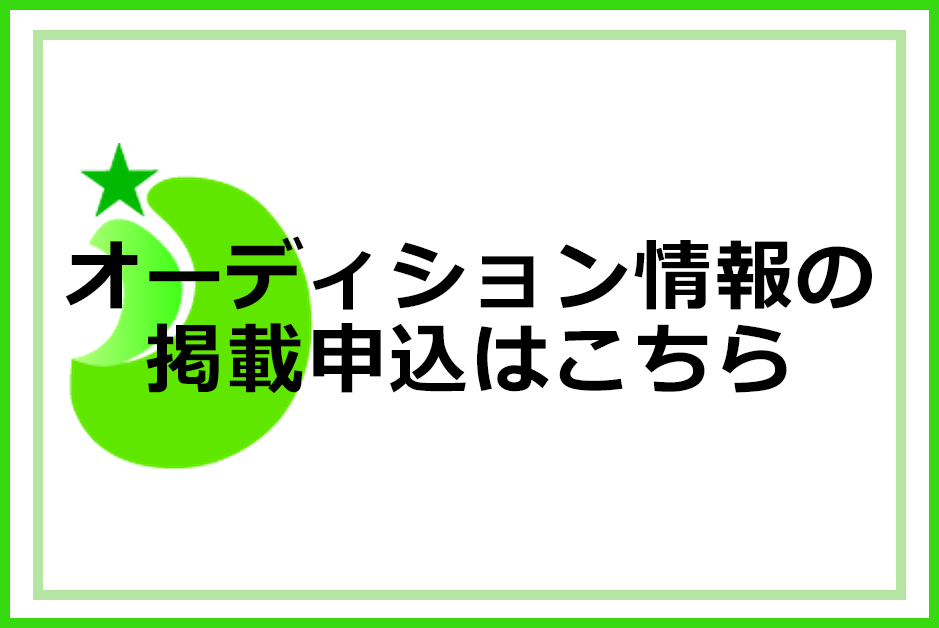ニュース
2024/08/05 19:01
俳優・笠原秀幸、俳優志望者へのメッセージ 「日常のセリフを自然に言うだけでも難しい。演技について考えることは、自分の生き方を見つめることになるんです」
小栗旬、田中圭、綾野剛、坂口健太郎、間宮祥太朗、木村文乃、赤楚衛二、葉山奨之、原菜乃華など、実力派俳優が多数所属するトライストーン・エンタテイメント直営の俳優養成/演技研究所『トライストーン・アクティングラボ(TSAL)』。トライストーン・エンタテイメント所属・笠原秀幸も、TSALにてレッスンを受け持つなど、後進の育成にも積極的に関わる俳優の一人だ。子役からスタートし約30年のキャリアを持つ笠原に、俳優、演技についての想い、TSALで若き俳優と関わることの意味、そしてこれから俳優を目指す人たちへのメッセージを語ってもらった。
■笠原秀幸インタビュー
「現場にいない時にどう過ごしているのかが芝居には出てしまうものなんです」
――笠原さんは年間の中で、トライストーン・アクティングラボのレッスンに登壇しているとお聞きしました。
「ここ2、3年ぐらいですね。ラボから受講生を教えてもらえないかという話をいただきまして。自分としては芝居を教えられる立場にはないと思っているので、教えるというより一緒にお芝居について考えるということであれば出来るんじゃないかと、年間で何度か、クラスを受け持たせていただいています。大変ではありますが、僕自身も学ばせてもらっています。先日、たまたま前原滉くん(TSAL出身で、トライストーン・エンタテイメント所属俳優)がここでデビューさんの取材を受けている日が、僕がクラスを受け持つ日と重なっていたので、前原くんにも同席してもらって一緒にやりました」
――そんなセッションが急に実現するのも、やっぱりトライストーン所属の俳優同士の繋がりのなせる業ですね。
「僕は割と所属俳優たちとコミュニケーションを取っているほうなんですが、本当に芝居が好きな人たちが多い。たまたまその日は前原くんでしたけど、おそらく違う俳優でも、僕が逆の立場でも一緒にやりたいと思ったでしょうね。教えるクラスの中には現役バリバリでやっている俳優もいれば、芸能事務所に所属したい、これからドラマや映画、舞台に出ていきたいという様々な俳優がいるのですが、芝居に向かっていくときは立場は同じ。彼らと過ごす時間は自分の勉強になるし、刺激になります」
――思いもしない角度からの発想の芝居が出てくることもありそうですね。
「自分は俳優を30年ぐらいやっているんですが、“この台詞をこう読むのか!”という驚きもあります。先日見学させてもらったクラスは、オーディションを想定した芝居のレッスンだったのですが、もらった台本で皆さんイメージを膨らませて、自分で衣装や小道具を用意して臨んでいました。僕自身は今までそういう準備をして臨むっていう発想は無かったなと思いました」
――かつては役を得るためのオーディションを沢山受けられたのでは?
「めちゃめちゃ受けましたよ! 体感で1000回くらいは受けたんじゃないかな(笑)」
――オーディションに臨むうえで大切にしていたこと、または掴んだコツのようなものはありますか?
「オーディションに受かる方法なんてみんな知りたいですし、僕も全く掴んでないです(笑)。でも選ぶ側の立場になって考えれば、その役柄に合う俳優だったかどうかでしかないんです。何百人受けたとしてもその役にハマる人は一人で、ほとんどの人は落選する。だから、その都度あまり落ち込まないようにするっていうことは、一つの秘訣かもしれないです。逆に短い台本の中で自分らしさを出し切れたならば、結果がどうあれしょうがないと思えるようになったかな。でも、いつまで経ってもオーディションに慣れてる人なんていないと思います。落ちたら落ち込みますし、自分がダメだったんじゃないかって思いますよね」
――最近は映像作品を演出されることもあって、オーディションで選ぶ側に回ることもあるそうですね。
「ここ10年ほど作り手として映像作品を作る機会があったので、自分の作品でラボの受講生をオーディションさせてもらったこともあります。逆の立場を経験したことによって、俳優に伝えられることもあるかも知れませんね。例えば先ほどの話のように、考えて服や小道具などを準備をしてきてくれた人は、第一段階として一緒にものを作ろうという意欲を感じるので、選ぶ側からすればありがたいことですし、何か発想をくれるんじゃないかということに繋がると思います。芝居にプラスアルファして、そういった感覚も考慮されないはずはないと思います」
――先ほど“自分らしさを出す”というお話がありましたが、それと“役を演じる”ということのどちらが答えなのかっていうのが難しいと感じます。
「それは多分、世界中で演じている俳優が常に考えていることなんだと思うんです。どんな役を演じたとしても、それが明るい役だろうが暗い役だろうが、自分で演じる以上は自分らしさが必ず出てしまう。分かりやすい言葉でいうと“素が出てしまう”ということが、演技の上で良いようにも悪いようにも言われるんですが、僕は“自分らしさ”は“どうしても出てしまうもの”だから、それでいいんだと考えています」
――演技について、ただ学校のように教えるのではなく、ラボラトリー=研究所として一緒に追究していくのが、トライストーン・アクティングラボらしさなのかなと思います。笠原さんはラボの特色・特徴はどこにあると感じていますか?
「僕は外部のレッスンもいろいろ見て来たんですが、例えば監督さんやプロデューサーさんのワークショップは、実際にお芝居をやらせてみる現場のような形式が多いですよね。ラボの場合は、オーディション形式のものや、カメラで実際に撮った場合にどう映るかとか、プロになって仕事の現場に行ってしまったら、立ち止まって考えられないようなことをかなり追究している。先生が様々な方法を試行錯誤しているので、ラボという言葉はぴったりだなと思っています」
――所属俳優の方も、現場の間に演技について見つめ直すために戻ってくるような、トレーニングジムのような役割もあるのではないかと思います。
「僕自身個人的にお願いして、ラボの先生に見ていただくこともあります。現場でOKをもらって、それが放送・公開されて評価されていくんですけど、そこで立ち止まって、実際この芝居はどうだったのか、どうやったらもっと良くなるかを考える上で、現場以外で客観的に見ていただく必要を感じます。現場は自分のための時間じゃないですし、学びはあっても学ばせてもらう場所じゃないので、原点に立ち返る場所としてラボは必要だと思います。芝居を野球に例えたら、今の自分が時速何キロの球を投げられているのか、変化球がどれくらい曲がるのか、そういったことを試せる場所だと思います。そういう場所があるだけでも心強いですね」
――笠原さんは10歳で俳優デビューしていますが、自分の演技についてはどのように確立していったのですか?
「子役事務所にいた時も、ちょっと斜に構えていたのであんまりレッスンに行かなかったですから。しっかりと発声や受け答えをとても丁寧に教えてくださる事務所だったんですが、割と早い段階でお仕事が決まって行ったので、現場で学ぶことが多かったんです。だから演技についてはずっと感覚的にやっていました。でも、20歳を超えたころから、その感覚がわからなくなってきてしまって。伊達にキャリアもあるから芝居ができると思われているし、自分でもできると思っているのに、実際思うようにできなくて苦しんだ時代がありました」
――感覚だけに頼って、考える基準が無かったと。
「まさにおっしゃる通り。考え方の基礎も無かったので、不安定な場所に立ったまま不安定なことをやっていたという感覚でした。もしかしたらそれでもうまく回ることもあるんでしょうが、僕の場合はあまりうまくいかなかった。でもそのことに気付くタイミングがあったという感じです」
■「現場にいない時にどう過ごしているのかが芝居には出てしまうものなんです」
――トライストーン・エンタテイメントの所属になったのはいつ頃ですか?
「27歳のときなので、ちょうど2010年。僕が所属になった時と、トライストーン・アクティングラボの設立が同じ頃だったと記憶してます。前にいた事務所が俳優の事務所ではなかったので、ここで俳優を続けるのは難しいよねというのを前事務所の社長さんと話し合って。そこで移籍先を探しているときに仲の良い小栗旬くんとの縁もあってここに来た、という感じですね。2024年の今ほどたくさん俳優も所属していなかったですし、いろんな意味で未知数でしたが、御縁を強烈に感じて、ここでやりたいと思ったんです」
――現在ラボで学んでいる人も、他で俳優をやっていた経験者から全くの初心者、元アイドルから元会社員まで、出自は様々です。そういう人たちが“演技”という下に様々な価値観をぶつけ合うのが興味深いですね。
「僕は、俳優だけをやっていたら俳優はできないと思っているんです。現場にいない時にどう過ごしているのかが芝居に出てしまう。どうしても自分が、自分の生き方が出てきてしまうものだなと最近改めて思っています。もちろん俳優として、技術的にその役に近づいていくことはできるんですけど、本質的なところが出来ている人には勝てない。だからいろんな生き方の人で集まるというのはすごく素敵だと思います。プロの現場でもミュージシャンや、小説家、お笑い芸人といった方々がいらっしゃって、そういう方々のお芝居がとても輝く瞬間を何度も見ています。それは芝居の技術だけではない何かじゃないですか? 彼らの生きざまに俳優が立ち向かっていったときに、面白いシナジーが生まれる瞬間を、多くの人が映画やドラマで味わっていると思います」
――そういう人の“輝く瞬間”を切り取ったものが作品に定着しているのだと思うのですが、逆に俳優はコンスタントにそれを出せないといけないですよね。
「そういう意味でも、俳優はやっぱり技術職ではあると思います。特に舞台演劇であれば、同じことを繰り返しながら、鮮度を保つというのも技術ですし、継続的に様々な作品で演じるのが俳優の仕事。演じるということについては、深く考えてしまうと、ものすごく深いところまでいってしまうものなんですよね…。それこそ最近、旬くんとお芝居について研究する時間があったんですよ。話の流れでこの場所を借りて、一緒に演じてみながら話し合ったりしました。作品にするために演じるという制限がないから余計に深く潜ってしまって、でも役者としては本当に楽しかった。
――今後、俳優でありクリエイターでもある笠原さんが、ラボと一緒にこんなことをやってみたいと考えていることはありますか?
「ラボのみんなは毎週ここに来て真剣にやっているので、みんながプロの俳優になったら嬉しいし、一緒にお仕事できたらいいなと思っています。ラボとしても定期的に作品を作っていますが、その回数がもっと増えればいいですし、僕自身、広島県の遊園地のプロデューサーをやっているので、舞台やスタジオだけではなく、そうした場所で一緒に演れる方と出会えればいいなと思っています」
――ラボにはどんな人に来てもらいたい、どんなに人にぴったりの場所だと思いますか?
「僕以外の所属俳優も定期的に見学に来ていたり、トライストーンという事務所とダイレクトな場所にあるので、プロの俳優になるためには近い場所にあります。そしてここに来ればまず“芝居をする”という非現実的なことが体感できます。脚本を読んで演じるわけですが、日常的な“おはよう”や“こんにちは”をただ自然に言うだけのことが大変だったりする。そんな壁にぶつかったりすることも楽しいかもしれないです。普段意識しないようなことを考えることは、結局自分の人生や生き方までを見つめることになるんです。そして、講師とラボの受講生が何十人もいる前でお芝居をするって特異なことだなと思います。撮影現場にいて“変なことしてるな”ってたまに思うんですけど、同じようなことを体感できるのは面白いと思いますよ」
――笠原さんもキャリアを重ねながら、現在放送中のドラマに出演するなど現役で活躍されている中で、以前とご自身の演技が変わったと感じることはありますか?
「結婚して、家族を持ったことで変わったかなと思います。お芝居が変わったかどうかは自分では判断できないんですが、少なくとも家族を持った上で、まだ俳優をやりたいと決意してそれを妻に了承をもらい、ここにいるということは当然、意気込みも想いも変わっているのは間違いないと思います。人生ってやっぱりどうしても、どうしようもなく演技にくっついてくるんですよね。先日お父さん役をやったんですが、以前とは感じ方が全然違いましたね。現在妻が妊娠をしているので、いずれ子供が生まれて、育てていく中で、また大きく違ってくるのかも知れませんね。自分の子供となると思い通りにいかないことだらけでしょうから。それは楽しみでもあります。台本の読み方も全然変わるのかな? 違わないとおかしいというか、本当に演技って生き方だと思いますから」
――最後になりますが、このインタビューを読んで、俳優の世界に飛び込んでみたいと思った人に、背中を押してあげられるようなメッセージをいただけますか?
「このインタビューを興味があって読んだ人も、たまたまたどり着いちゃった人もいると思うんですけど。僕自身は、あんまり失敗するのは怖くなくて。それよりも失敗が怖くて挑戦しなくなるほうが怖いんです。だから少しでも俳優や演技に興味を持って挑戦してみたいなと思っているなら、どんどんやってみてほしいなって思います。ここに来て何か失うことはない。学校だったりバイトだったり仕事ではなく、芝居をする機会を持つことで、本質的なところがかなり豊かになっていくと思う。これも一つのご縁だと思ってやってみたら、予想もしない人生になるかもしれませんよ」
■笠原秀幸プロフィール
(かさはら・ひでゆき)●1983年4月29日、東京都出身
1995年NHK日中共同制作ドラマ『大地の子』の主人公、陸一心(上川隆也)の少年時代役でデビュー。その後も映画『沈まぬ太陽』で仲代達矢らと共演。映画『リリイ・シュシュのすべて』『クローズZEROII』など数多くの作品に出演している。
現在、テレビ東京「しょせん他人事ですから 〜とある弁護士の本音の仕事〜」木下浩之役で出演。映画「本心」(監督:石井裕也)が2024年11月8日(金)公開。